『何もしないプロデュース術』(小山登美夫著)に共感する 2009/09/21
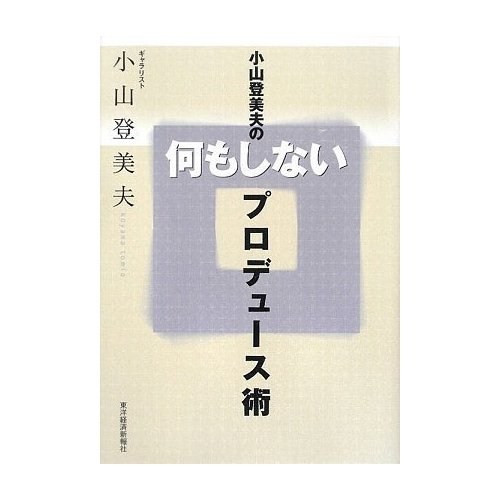
![]()
大きな共感を覚えた一冊である。『何もしないプロデュース術』小山登美夫著(東洋経済新報社)。
筆を走らせた小山登美夫という人は、アーティストの村上隆や奈良美智などを世に送り出した気鋭のギャラリストである(ギャラリーと画廊は違うと小山は云う)。
彼の手法のみごとなところは、何もしない! 相手(アーティスト)に任せる! 任せながら操る。ということに徹していることだ。それだけを云いたくて、彼はこの本を書いた。きっとそうに違いない。
「何もしない」とは「な〜んにもしない」とはまったく違うことである。
指揮者カラヤンの有名な言葉に「ドライブするな キャリーしろ」がある(以前にも書いた)。ドライブもキャリーも乗馬の用語である。ドライブは、馬にまたがり、手綱にぐいぐいと力を入れながら操る方法のこと。一方、キャリーは、馬に自分の意思で自由に動いていると思わせておいて、きちんとその動きをコントロールすることだ。カラヤンはオーケストラで重要なのはこのキャリーだと教える。
これは何もオーケストラにだけ言えることではない。その道のプロ同士や経験豊かな人々が顔をあわせる会議では、時として意見がぶつかることがある。たとえ同じ志を持っていても、経験という土俵がまったく違うからだ。
人は「経験した土俵」につねに執着する。結果、それを相手に押し付け、そうして手の届く範囲でしかプランを立てなくなる。そのために「わたしが知らない」という理由で、大切な人物を企画案のキャスティングからはずしてしまうことすらある。勘違いしてはいけない。企画そのものが「あなた」をターゲットにしていない。そもそも「わたしが知らない」などと大きな声でいうものではない。むしろ恥ずべきだ(知らないことはけっして悪いことではない。むしろ自分は何を知らないかを知ることは重要)。そうしてこっそりとでもいい、勉強すべきだ。ただし、サイトでこそっと名前だけ入れて検索しても知ったことにはならない。
話が逸れた。
この書物の詳細については、近々書評にも書くことになるだろう。
![]()
バックナンバーはここ↓から。「表示件数」を「100件」に選択すると見やすくなります。