驚愕すべき内容である! 〜またまた東京大学出版会の仕事
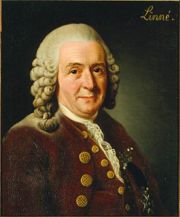
本屋さんで何気なくある本の内容見本を手に取ったのがいけなかった。寝ても覚めてもその本がちらつくのである。その見本は、東京へ三回、神戸へ一回、名古屋へ一回、富士へ三回、伊豆へ二回もわたしと旅をともにした。
その間、内容見本さんは、バーのカウンターでわたしに口説かれ、スタバで穴の空くほど見つめられ、愛車の助手席で乱暴に扱われ、熱海の海岸で直射日光にじりじり焼かれ、イタリアンレストランで一方的に講釈を聞かされ、ホームの立ち食いそば屋で汁(つゆ)をかけられた。
その本とは、『生物学名大辞典』(平嶋義宏著 東京大学出版会)。どうやら今年は博物学者リンネ生誕300年らしい(本書はそのタイミングに合わせた出版ではないそうだ)。
そもそもリンネとわたしの出会いは、小学生四年生の理科準備室にまで遡る。その埃っぽい書棚で、書名までは覚えていないが、とにかくそこに置かれていた分厚い事典のような豪華本の中で、ビュフォンやフィリップ・ヘンリー・ゴッスやオーデュボーンやシーボルトや高木春山と共に出会うことになる。なかでもリンネとゴッスは以来わたしのアイドルとなった。
ゴッスは『アクアリウム』の著者としてあまりにも有名で、それまでの博物画を一変させた。彼が現れるまでは、死んだ魚を、さも生きているかのごとくスケッチしたり、あるいは陸上から観察し、水中の魚を想像で描いたりしていた。しかしゴッスはなんとガラスの水槽をつくることで、生物を真横から観察し、生き生きと描き出すことに成功した(この水槽がまた売れに売れた)。なんと19世紀のはじまりのことである。
一方、リンネの業績を一言でいうなら「分類」と「命名」である。これは驚異的な仕事である。詳しいことは書ききれないが、あれから2世紀経った今でも、基本的に彼の編集方針「二名式」は、継承されているのである。
話をゴーインに引き戻す(ほんとうは喋り足りない)。この『生物学名辞典』のすごいところは、あらゆる学名の語源とその意味を驚異的なボリュームで編纂していることだ。大袈裟に言うのではない、生物学の辞典では歴史に残る偉業である。わたしもことあるごとに新刊を手に取っているが、ここまですばらしい内容は見たことがない(たしか、地質学には似た仕事はあったが、ただし、この辞典には質、量ともに遠く及ばない)。おまけに、自分が博物学者になった気分になれる「命名ドリル」までついている。
あ、そうそう、けっきょくこの辞典、購入しました(HATORIさん、RIKAさん、またまたありがとうございます)。しばらくこの辞典をベースキャンプに、知の世界を渉猟してみるつもりである。
http://www.utp.or.jp/bd/978-4-13-060215-0.html

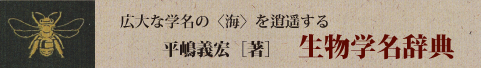
理系ならずとも、知の歴史を覗き、好奇心を満たすことに敏感な人は、絶対に手元に置くべき辞典である。必見である。わたしが保証する。
まだまだ書き足りなのはわかっているが、きょうは天気のせいか、腱鞘炎がひどい。手首に激痛。もう書けない。後ほど赤を入れることにしてとりあえず、アップする。
※トップの人物画像は博物学者リンネの肖像。
※以下、この辞典の画像ではないが、わたしを夢中にさせる博物画たちである。美しいと思いませんか。
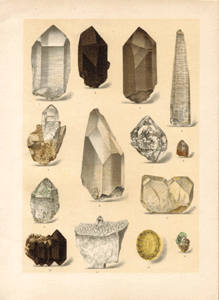
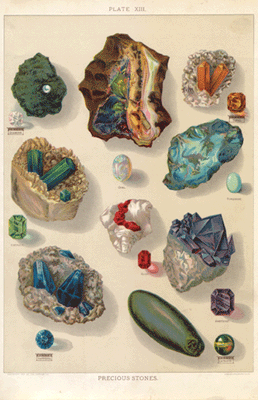
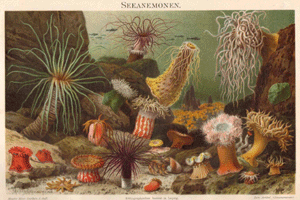
※例えば、今回の日記でだいたい何文字ぐらいを打っているのかを調べてみたら、1400文字程度だった。原稿用紙3枚半。なるほど、それなりに書いているのである。読んでくださる方は大変なことである。